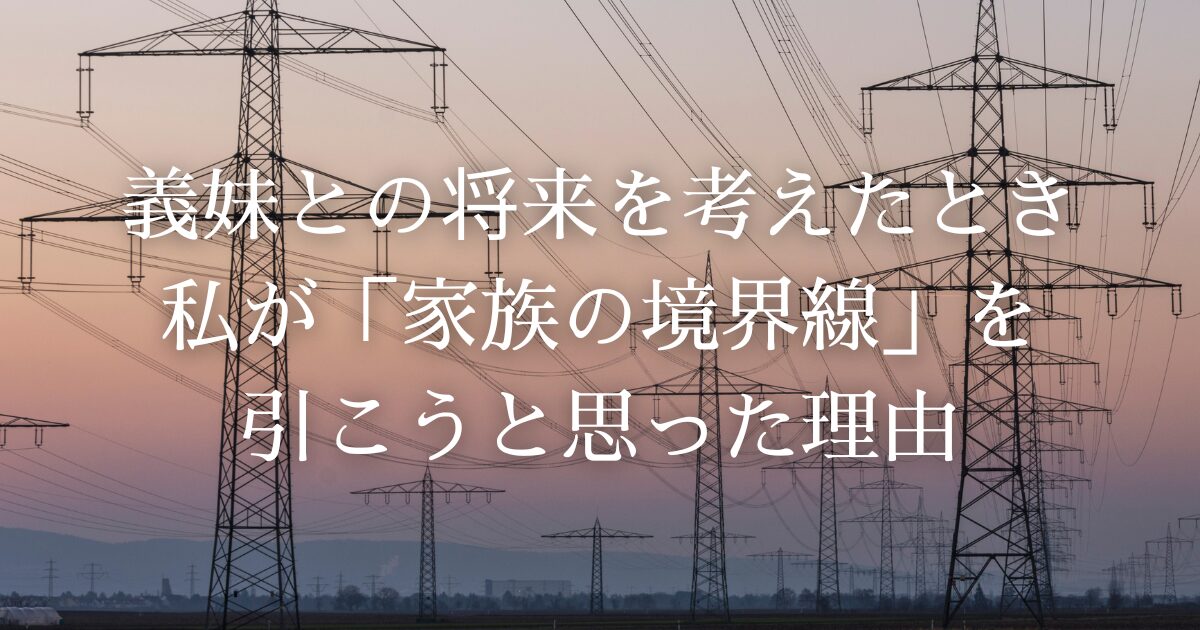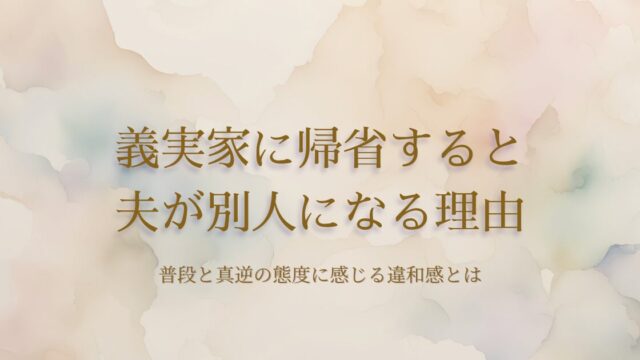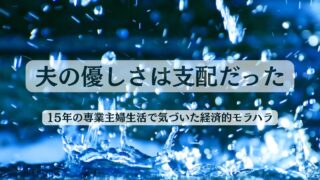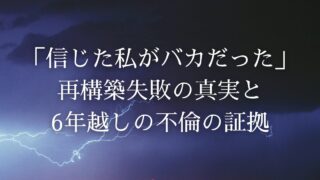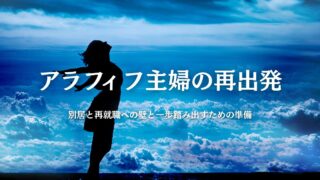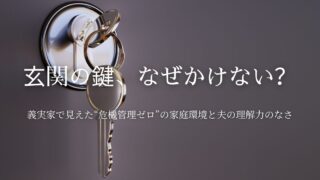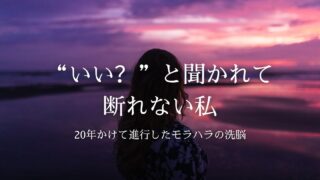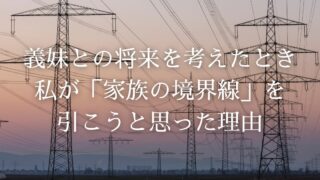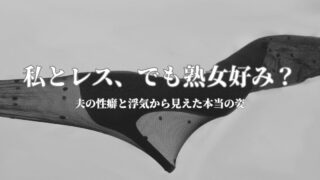夫には独身で実家暮らしの妹がいます。素直でまじめな性格の彼女ですが、発達の遅れや精神的な病気と向き合いながら生活しています。私たち家族との関係や将来の介護問題を考えたとき、私は「家族とは何か」「どこまで関わるべきか」について真剣に向き合うようになりました。この記事では、そんな義妹との関係性と将来への不安、そして私が考えた「家族との距離感」についてお話しします。
義妹との出会いと20年の関係
18歳だった彼女との出会い
私が義妹と初めて会ったのは、彼女がまだ18歳の頃。今では38歳になり、20年以上の付き合いになります。当時からアニメや漫画、特撮が大好きな「オタク気質」で、実家でのんびり暮らす姿に「マイペースな子だな」と思っていました。
少し気になる発達の遅れ
夫から義妹は「成績はずっとオール1だった」と聞かされており、通知表も見せてもらったことがあります。家族の名前を漢字で書けなかったり、英単語が読めない、カタカナを書き間違えたり読み間違える場面もあり、「もしかして学習障がいがあるのかもしれない」と感じたこともあります。
義妹の精神疾患との向き合い方
統合失調症の発症と治療
義妹は十数年前に統合失調症と診断され、今も薬を服用しています。発症直後は幻聴や幻覚に悩まされ、「鼻から考えが漏れる」などの症状を話していたこともありました。幸いにも早期に医療につながることができ、現在では症状をコントロールしながら日常生活を送っています。
働き続けられていることのすごさ
高校卒業後に就職した職場で、20年以上も変わらず勤務している義妹。
職場や家族のサポートがあるからこそ続けられているのだと思います。精神疾患を抱えながらも働き続けている彼女を、素直に「すごいな」と思います。
それでも拭えない「将来への不安」
子どもが感じる違和感
義実家へ行くたび、義妹がじっと見つめてくることがあり、子どもが「ちょっと怖い」と話すことも。おそらく本人に悪気はなく、無意識の行動かもしれません。でも、私たちにとっては無視できない問題です。
義母亡き後の生活はどうなる?
現在の義妹は、ほとんどの生活面を義母に支えられています。料理、掃除、日常の管理も含め、一人での自立は厳しいのが現実。義母が亡くなった後、義妹を誰が支えるのか…私たち家族にも重くのしかかるテーマです。
「私と子どもは関わらない未来」を選ぶ理由
家族であっても、限界はある
私自身は一人っ子で、兄弟姉妹に支え合うという経験がありません。そのため、夫が「妹の面倒をみないといけない」と思っていたとしても、私には簡単に共感できない部分もあります。
子どもに背負わせたくない未来
もし夫が先立った場合、義妹の面倒を見るよう、私や子どもに求められる可能性もゼロではありません。だからこそ、今のうちに家族の線引きをしておきたい――そんな思いが強くなっています。
夫の不貞とモラハラ――崩壊した夫婦関係と、私の決断
そして何より、私が「家族の境界線」を明確に引こうと決めた一番の理由は、夫の不貞行為と日常的なモラハラによって、すでに私の中で夫への信頼が完全に崩壊していることにあります。
これまで幾度となく裏切られ、傷つけられてきた私は、現在離婚を真剣に考えている段階にあります。そしてその決断に向けて、証拠の収集や弁護士との相談など、水面下での準備も着々と進めています。
夫婦という基本の土台が崩れてしまった今、私と子どもがこれからの人生を安心して生きていくためには、「元夫の家族」との関わりを断つという選択が必要不可欠です。離婚後までその関係を続ける理由は、もうどこにも見当たらない――それが、私がこの未来を選んだ決定的な理由です。
関連記事
👉義実家に帰省すると夫が別人になる理由|普段と真逆の態度に感じる違和感とは