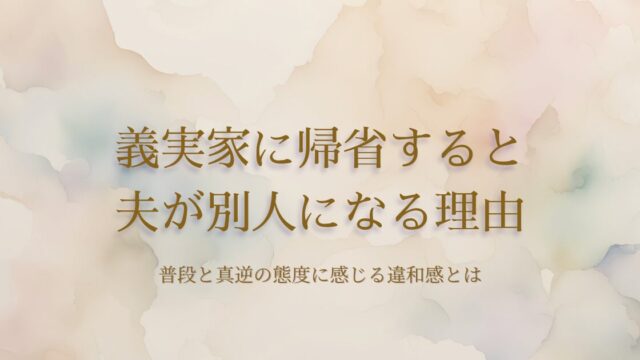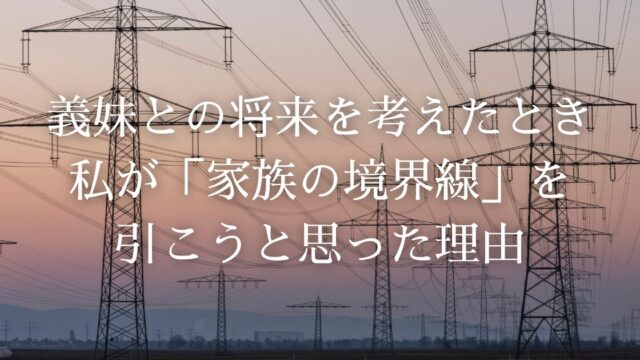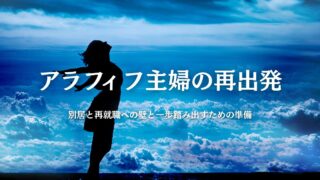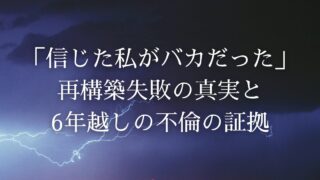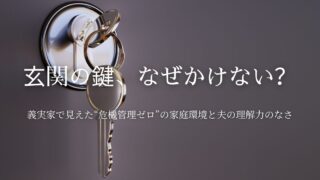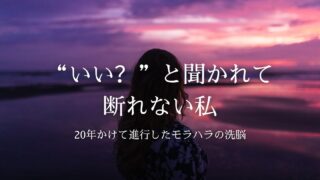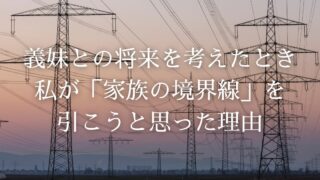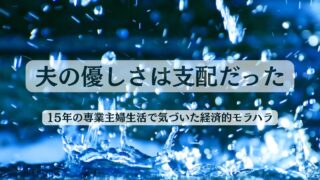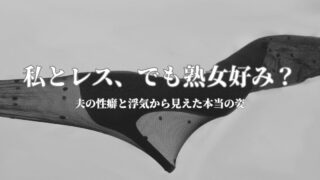あなたの家では、玄関の鍵を日中どうしていますか?
義実家では、今でも日中は玄関の鍵をかける習慣がありません。それが当たり前だった夫は、結婚後も「戸締まり」への意識が驚くほど低く、何度も恐ろしい思いをしました。
今回は、義実家のゆるすぎる防犯意識と、それに影響された夫の危機管理能力のなさ、さらには私や子どもとの“会話が噛み合わない”日常を振り返ります。小さなすれ違いに見えるけれど、その奥にあるのは「信頼」や「安心」の崩壊でした――。
義実家の防犯意識は“昭和のまま”に止まっていた
義実家では、今もなお日中に玄関の鍵をかける習慣がありません。
実は、私の実家も昭和50年代の頃は鍵をかけていませんでした。近所付き合いが濃く、誰がどこに住んでいるか全員が顔見知りで、空き巣などの心配がほとんどなかったからです。
しかし、時代は変わりました。防犯意識が問われる事件も年々増え、私の実家も現在ではきちんと鍵をかけるようになりました。
ところが義実家はというと、住宅街の丁字路の突き当たりという、目立ちやすい立地にもかかわらず、今も鍵をかけないことに驚きます。
過去には同じ市内で立てこもり事件まで起きていたにも関わらず、義母が夜になってやっと鍵を閉める程度。日中は誰でも自由に出入りできてしまうような状況なのです。
危機管理能力ゼロの夫と“鍵をかけない文化”
そんな家庭で育った夫も、鍵をかけるという習慣がありませんでした。
結婚後、私たちが暮らす家でも夫が玄関の鍵をかけ忘れることが頻繁にありました。
朝起きて玄関を見ると、まさかの開けっ放し。
何度この光景にゾッとしたかわかりません。
注意しても、夫は「うん」とだけ言って出勤していき、何の危機感もなし。
私は寝る前に毎晩、玄関の鍵がかかっているか確認するようになりましたが、夫が飲んで深夜に帰宅した日はどうしても確認ができないことがあり、不安が募るばかりでした。
挙句の果てには、夫が子どもに
「ママから玄関の鍵が開けっぱなしだったって“報告”されたんだけど」
と話していたことを後から聞いて、愕然としました。
私は報告したつもりではなく、「危ないから気をつけて」と伝えたつもりだったのですが、夫にはただの“情報共有”程度にしか受け止められていなかったのです。
伝えても伝わらない?夫の理解力に限界を感じる日々
夫と話が通じないことは、この1年で特に顕著になりました。
複数の女性との不倫、性依存、義両親からの性格的な影響など、要因はいろいろ考えられますが、どれも確証はありません。ただ一つ言えるのは、こちらがどれだけ丁寧に説明しても、夫には言葉が通じないという現実です。
具体的に説明しても、
「え?何言ってんの?意味わかんないんだけど」
と一蹴されることもありました。
この傾向は子どもに対しても同じだったようで、子どもも
「ちゃんと伝えてるのに“わかんない”って言われる。
こっちの言い方が悪いみたいに言われるのが嫌」
と私に打ち明けてきました。
私と子ども、両者が同じように感じていたのです。
これはもう、私たちの伝え方が悪いのではなく、夫側に問題があるとしか思えませんでした。
安全も安心も築けない家庭に、未来はあるのか?
家庭とは、安全で安心できる場所であるべきだと思います。
しかし、私たちが暮らしてきた家には「戸締まりの安心」さえありませんでした。
危機感のない家庭環境で育った夫は、そのままの感覚で私たちとの暮らしを続け、鍵の重要性さえ理解しようとしなかった。
何より問題なのは、私が感じた不安や不満が、夫にはまるで“伝わっていなかった”ことです。
これは戸締まりの話に限ったことではなく、家庭全体においても同じ。
私の話は「報告」でしかなく、危機感も責任感もない夫の行動には、夫婦の信頼関係を築く基盤さえ見当たりませんでした。
伝わらない相手と暮らすということ
言葉が通じないというのは、外国語の話ではなく、同じ言語でも「価値観が合わない」「受け止めようとしない」人との間にも起きることです。
義実家の防犯意識の低さに始まり、それをそのまま引き継いだ夫。
その夫と私たち家族の間には、埋められない溝ができていました。
私は今、安心して眠れる家と、言葉がきちんと届く関係を築ける未来を求めています。
この日々の中で得た教訓は、「常識は人それぞれ。だけど命と安心は、自分で守るしかない」ということでした。
関連記事
👉義実家に帰省すると夫が別人になる理由|普段と真逆の態度に感じる違和感とは
👉義妹との将来を考えたとき、私が「家族の境界線」を引こうと思った理由